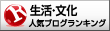御香典や喪中はがきに使う「薄墨」の理由

喪中はがき作成
今年の春に妻の祖母が他界し喪中はがきを作ることになりました。
喪中はがきの一般的な書き方やマナーを知っておきたいとネットで調べ、さらに我が家が受けっ取った喪中はがきを引っ張り出して実例として調べてみました。
この内容については別サイトでまとめていますが、その喪中はがきにまつわることを調べているうちに「薄墨」という言葉に遭遇しました。
薄墨なので赤字ではなく「薄墨」と表現した方が良いかもしれませんが。
【喪中はがきの書き方】実際に受け取った実例をまてめてわかったこと | 途次大志の備忘録
薄墨を使う理由
喪中はがきなどの弔時の手紙では文字を黒色ではなく薄墨(灰色)を使う方が望ましいようです。
ただ別サイトにもありますが今では灰色ではなく黒色(黒書き)も一般的になり、実際に我が家が受け取った喪中はがきの多くは黒色で書かれています。
なぜ薄墨を使う方が望ましいのかを調べました。
古くからのマナーやしきたりなので諸説あると思いますが、という前置きを書いておきます。
諸説その1
「あまりの悲しみで涙が墨(黒色)に落ちて薄まって薄墨(灰色)になった」
なんとも詩的な表現だなと思いませんか。
文字の色に感情を込めるという風情を感じます。
こういう心遣いは大切にしたいですね。
諸説その2
「急な出来事でゆっくり墨をする時間がなく薄墨(灰色)になった」
時間的にそこまで逼迫していない喪中はがきではこの理由はピンときませんが、御香典の文字色についてはピンときます。
確かに御香典に包むお札も結婚式の時のようなピン札ではなく、むしろピン札を一回折るなどしてピン札感を失くす方が良いというのを聞いたことがあります。
薄墨という文字色を使うことで「あまりに急で驚いている」という想いを表現しようという心遣いはとても大切にすべきもののように感じます。
伝統色の薄墨色
今では喪中はがきや御香典の文字色として使われている薄墨ですが、伝統色とし「薄墨色」があるようです。
「薄墨色」は赤字ではなく「薄墨色」で表現したほうが良いですよね。
この薄墨色、伝統色と言われるだけあって平安時代から使われているようです。
しかも平安時代から訃報を知らせる手紙に使われており、文字色としての用途としては現代と共通していることに驚きます。
手紙の文字色としてだけでなく、喪服の染色としてもこの薄墨色が使われていたようです。
まとめ
今回、薄墨が薄墨色として平安時代から今と同じ用途で使われてきたことを知りました。
こういった風習は大切にしたいものです。
ただ喪中はがきを作る際に文字色を黒色から薄墨に変えると料金が上がってしまう場合もあります。
家計的にも予算重視という考え方も大切なので、そこは各自の判断で今は許されるのでしょう。
ただし薄墨には伝統的な風情のある背景があるということだけは知った上で黒色(黒書き)を使用するということが望ましいのかもしれません。